fibonaは意見と人が交わる場所。 新メンバーが語る、「デジタル×コミュニケーション」の可能性
2022.07.13
資生堂の研究所が“外部の知と人の融合”を掲げて推進するオープンイノベーションプログラム「fibona」。3周年となる2022年は、過去最多となる9名が新メンバーに加わった。
新メンバーは、なぜfibonaに参加しようと思ったのか。コロナ禍でコミュニケーションのあり方も大きく変わるいま、デジタルの可能性について、どう考えているのだろうか。
fibonaのイベントに積極的に参加してきた岩永慎也、「S/PARK
Studio
美活ジム(以下、美活ジム)」のSNSを運営している岩下志織、エクスペリエンスデザイナーとして活躍する新井隆士の3人が語り合った。
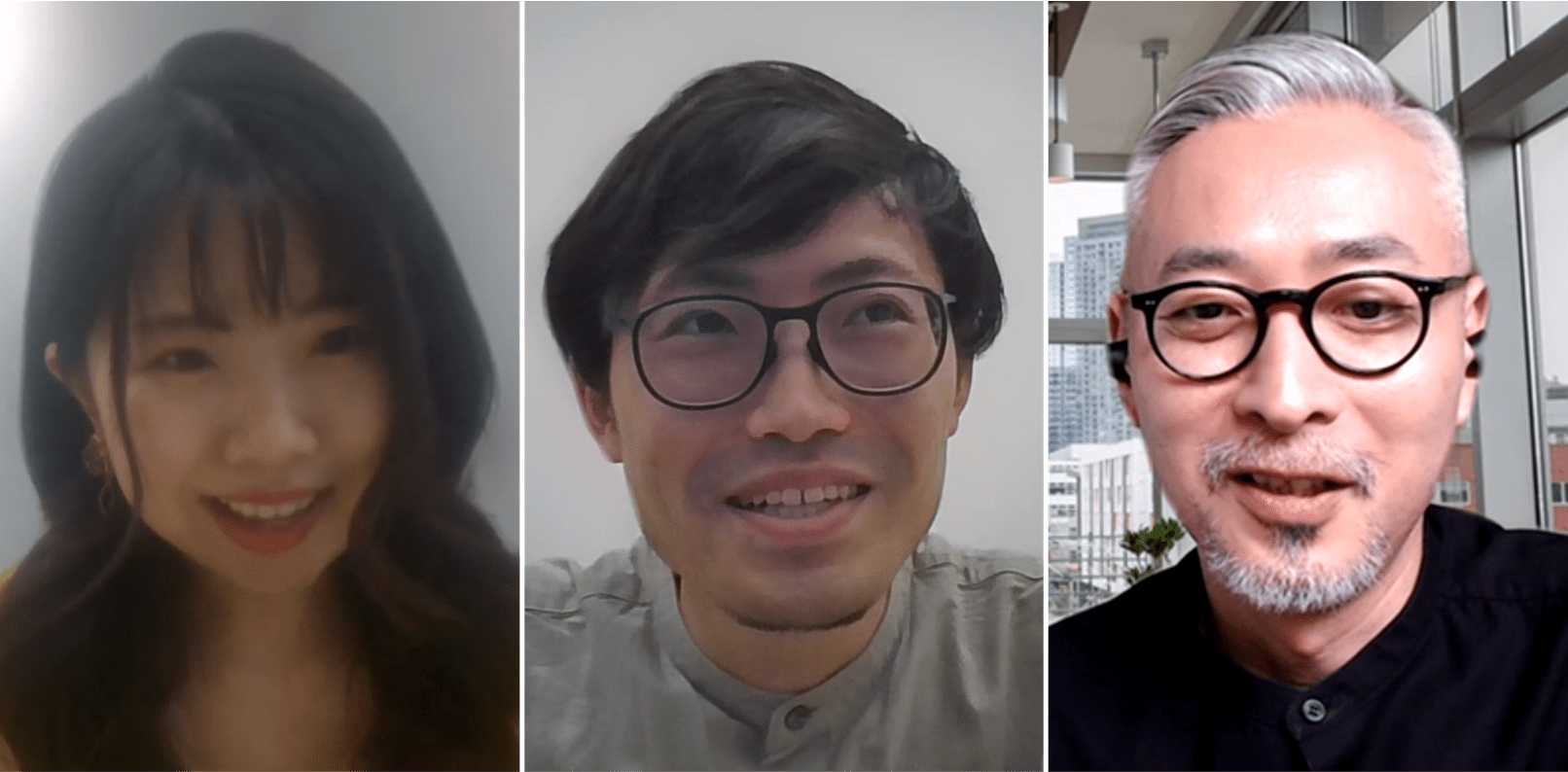
エクスペリエンスデザイナーやSNS運営担当、多様な新メンバーが集うfibona
──みなさんの普段の業務と、fibonaに参加した経緯や担当プロジェクトについて教えてください。
岩永:
普段はブランド価値開発研究所で、主に化粧品の原料の安全性評価に関する研究をしています。以前からfibonaの活動には興味を持っていて、イベントには積極的に参加してきました。今回は、より当事者意識を持って関わりたいという気持ちから、思い切って公募に手を挙げてみました。
fibonaではイノベーションが生まれる土壌をつくる「Cultivation」の企画運営メンバーとして、「Around Beauty Meetup」などのイベントを通じて、社内外を問わず、ビューティーに関して広く自由に意見交換する場の提供に取り組んでいます。
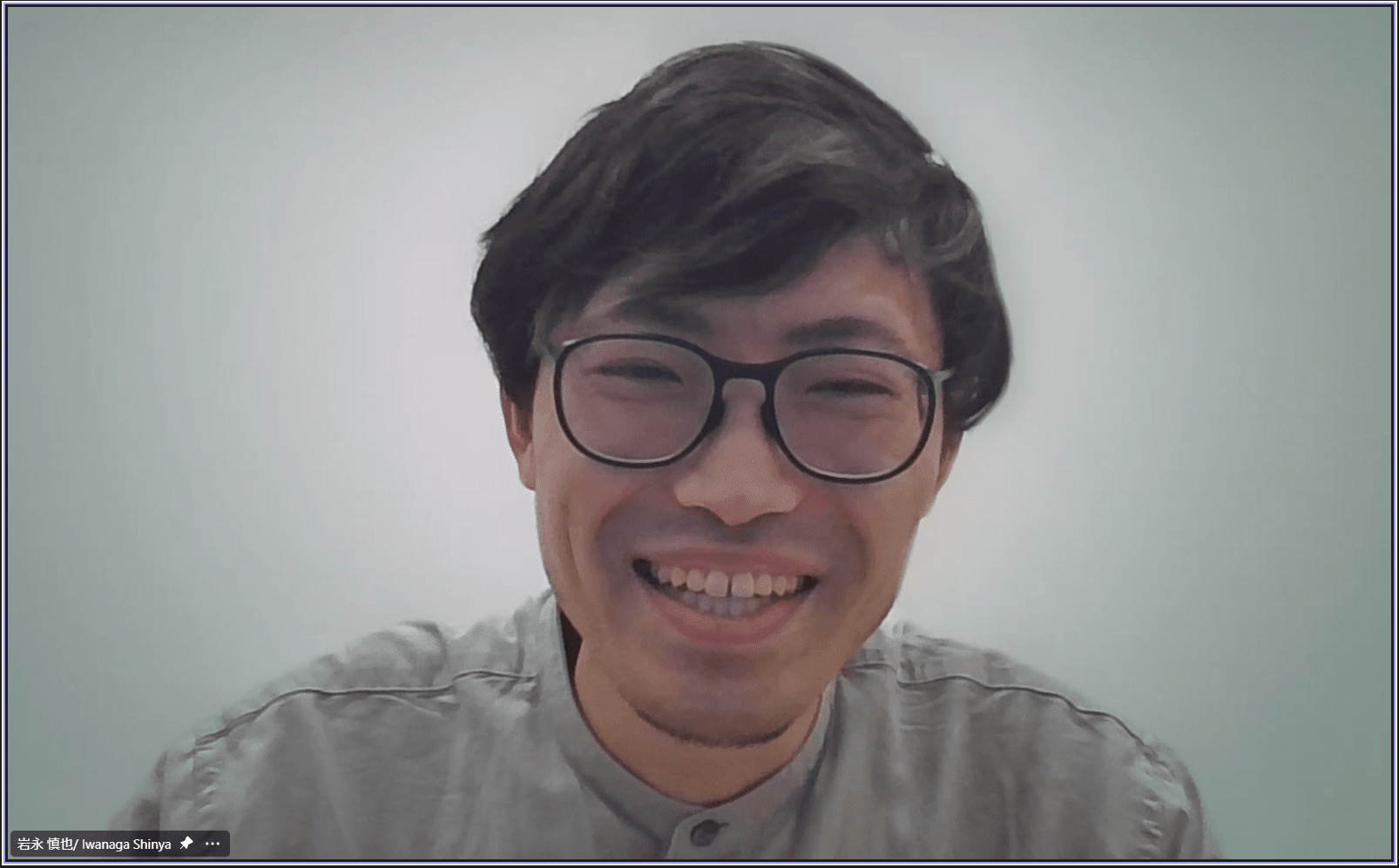
岩下:
私はブランド価値開発研究所で、主にマスカラや口紅などのポイントメイクアップ製品の開発をしています。2021年からは、資生堂研究員が開発した、肌と表情のセルフケアレッスン「美活ジム」の活動にも参加していて、Instagramの公式アカウント
を立ち上げたり、公式LINEを作ったりするなど、主にプロモーションを担当しています。
fibonaには、美活ジムの活動を見ていたメンバーの方から声をかけてもらって参加することになりました。これまでの経験を活かして、活動の周知などプロモーションの仕事を担当する予定です。
新井:
私はもともとUI/UXデザインの仕事をしてきて、2018年に資生堂に入社し、クリエイティブ本部でキャリアをスタートしました。2022年4月からは資生堂インタラクティブビューティーで、お客さまの体験作りなどを担当しています。最近では、研究所の成果をビジネス化するプロジェクトにも、エクスペリエンスデザイナーとして関わりました。
fibonaには以前から参加したいと考えていて、とくに新規事業の立ち上げに興味を持っていました。2021年末の社内イベントに参加して、既存メンバーの方に「どうしたらメンバーになれますか?」と聞いたところ、公募していることを知り、手を挙げました。
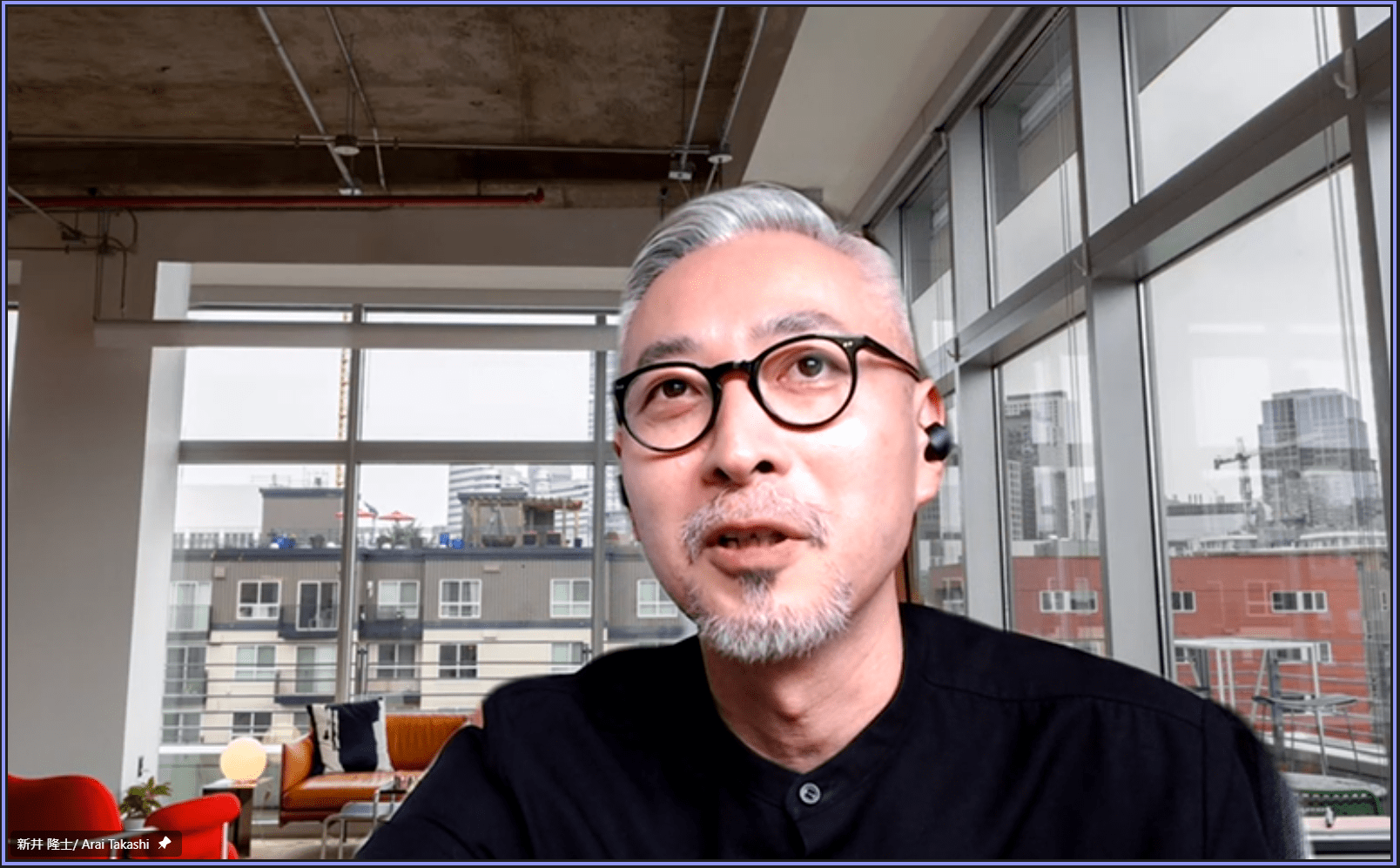
──fibonaの活動のどんな点に魅力を感じていますか?
岩永:
ビューティーとは、形も正解もない、ある意味で哲学のようなもの。その在り方や未来について、決まったメンバーとだけ話していると、どうしても意見が凝り固まってしまいがちです。そんななかで、社内外の人とフランクに意見交換できるfibonaのイベントが、とても貴重な場に映ったんですよね。
印象に残っているのは、クラフトビールを製造・販売しているヤッホーブルーイングの方が登壇した「Around Beauty Meetup #8」のイベントです。年齢やライフスタイル、性格などを詳細に描いてターゲットを絞り込み、少数の熱狂的ファンを獲得しようとするブランド開発のアプローチは、「製品を広く多くのお客さまに届けたい」と考えがちだった私にとっては目から鱗でした。
また、fibonaには、個々がそれぞれにやりたいことを尊重しあいながら議論を深めていくような雰囲気があります。そこは、社内で行われている他の取り組みとは違った魅力だと感じますね。

岩下:
資生堂に入社し研究員として働くようになって、化粧品の研究員たちは、個々にやりたいことや熱い思いを胸に秘めていることを知りました。しかし同時に、入社前の私がそうだったように、一般のお客さまは研究員の胸の内を知る機会がほとんどないということにも気づきました。
fibonaは、資生堂の社内と外部が交わり合う場所。ここでなら、研究員たちの美に関する思いや知見、開発のストーリーなどを発信し、お客さまに届けることができるのでは、という可能性を感じています。美活ジムのInstagramも同じような気持ちで立ち上げ、運用しているので、その経験も生かしていきたいです。
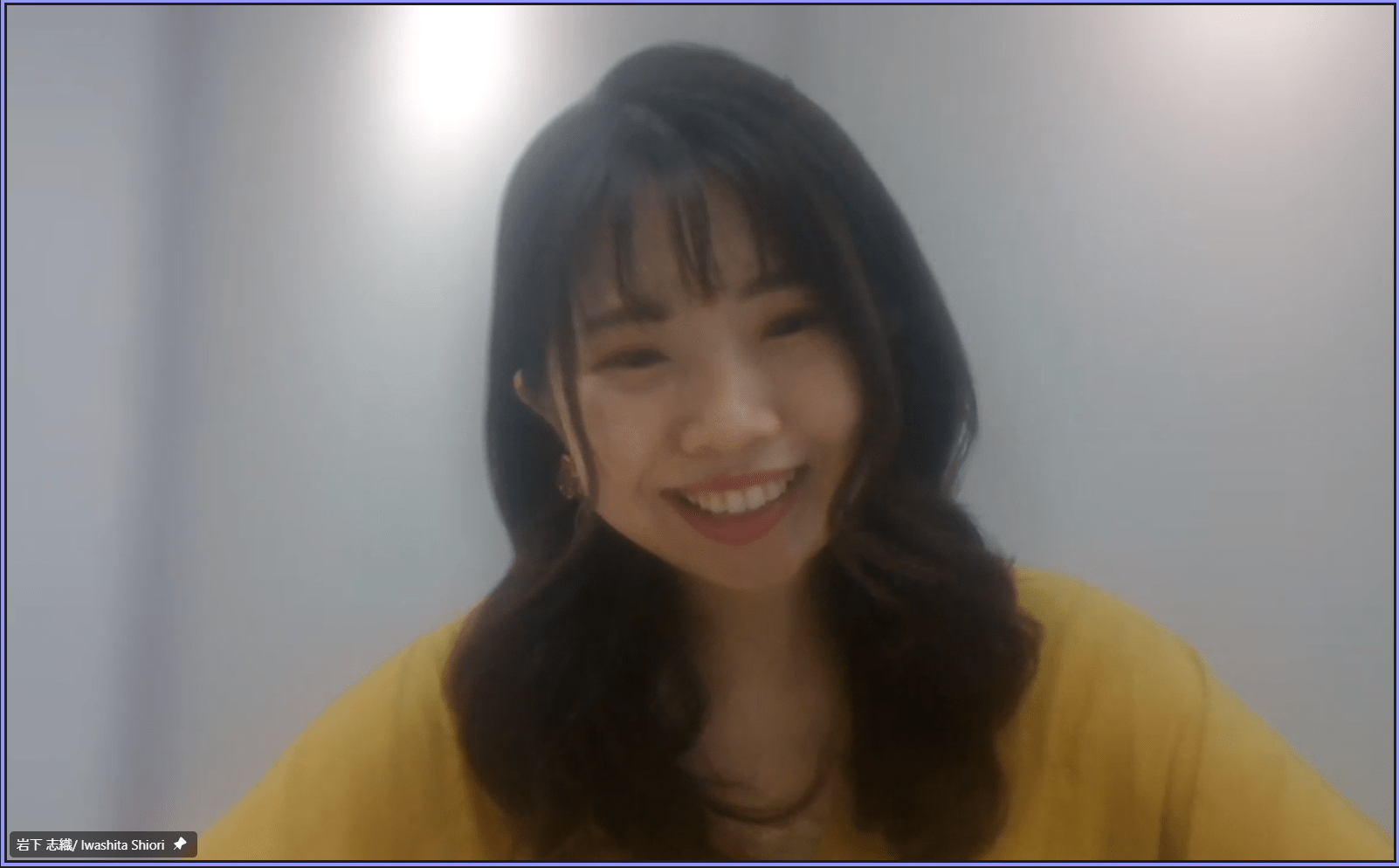
新井:
研究員の思いや過去の研究実績、表に出ていない技術を、デザインやストーリーテリングなどで可視化して表に出すというのは、新しい価値提供のひとつとして、私も取り組みたいところです。事実、ブランドのマーケティングをお手伝いしていても、お客さまの関心は機能や成分だけでなく、開発のストーリーなどにも向いていると感じるんですよね。
fibonaでのスタートアップとの共創にも関心があります。資生堂に入社して4年目に入りましたが、安全性、確実性を求めるあまり、スピード感や推進力に欠ける部分もあると実感しています。fibonaでは、社内外の様々な職種の人たちが集ってプロジェクトを進めることで、スタートアップのようなスピード感や柔軟性と、資生堂の強みである伝統や歴史を掛け合わせた、よりよい物作りができるのではと期待しています。
コロナ禍で感じたコミュニケーションの変化と可能性
──SNSの普及、新型コロナウイルスの流行などにより、コミュニケーションの形が大きく変化しました。みなさんは、デジタルにどんな可能性を感じていますか?
岩下:
コロナ禍、美活ジムではInstagramで美容の基礎知識や最新研究について発信し、感染症対策を実施した上でリアルレッスンも開催してきました。その経験を踏まえて感じるのは、オンラインとオフラインでは、伝えられる相手や伝えられる情報の深さが違うということです。
Instagramなどを通じたオンラインコミュニケーションの強みは、リアルで会えない人とつながれるところ。リアルで行うレッスンは、どうしても研究所のある横浜周辺にお住まいの方が対象になりますが、Instagramでリーチしている人を見ると、神奈川県だけでなく、東京都や大阪府、さらには海外にまで情報が届いていたりと、想像以上に広い範囲でつながりを持てています。
一方リアルで行うレッスンでは、より深い情報を一瞬で伝えられる実感があります。Instagramの投稿では、研究員の知識を共有することはできても、美活ジムがどんなところかまでかは伝わらない。「百聞は一見にしかず」といわれるように、密なコミュニケーションはリアルな場でやるほうがうまくいくし、伝わる実感があります。

新井:
インターネットやSNSの普及で情報が溢れるようになり、情報をカスタマイズして消費することが普通になっています。そのため、お客さまは「瞬時に適切な情報を手に入れたい」という欲求を持つようになり、マーケティングが難しくなっているのを感じますね。関係のない広告、興味のない広告が出ると強い不快感につながってしまうので、できるだけお客さま一人ひとりにパーソナライズした情報を提供することが課題になります。AIなどのデジタルツールは、その解決策になりうるのではと考えています。
この先、デジタル技術が発展していけば、お客さまとのコミュニケーションのあり方も、パーソナライズされていくのではないでしょうか。資生堂の強みは、ビューティーコンサルタントがお客さまとリアルにコミュニケーションできる店頭の場を持っていること。リアルな場でのコミュニケーションは、情報量が多く密度も濃い。今後は、そうしたコミュニケーションが、デジタルでも体験ができるような未来が来ればいいなと考えています。
テクノロジーが進化していけば、最終的には人はただの入れ物になって、拡張したデジタル空間のなかで現実を超えた体験が可能になるのかもしれません。そう考えるとワクワクしますし、どんな新たなビジネスが生まれるのかも楽しみです。
岩永:
ここ数年、オンラインの会議や打ち合わせが当たり前になり、コミュニケーションとは何かを考え直す機会になりました。「顔が見えないのに、複数人の人が話す声がする」「何かを話しているのにミュートになっていて聞こえない」といった新しい経験を通して発見したのは、コミュニケーションとは複数の要素が組み合わさって成立しているということです。
今まで人と約束をするときは「日にち・時間・場所」をセットにして考えていましたが、「場所」は必須ではなくなったと気づきました。逆に、場所をわざわざ設定するのであれば、「自然のなかで」「いい音楽の流れる環境で」「インスパイアされるようなデザインの空間で」など、演出的な効果を狙うことができるのだと。
場所を問わず、姿を見せることもなく、つながることができるデジタルでのコミュニケーションは、私たちを見た目や属性といった物理的な制限から解放してくれるのかもしれません。一方で、タイムラグがなく、誰にも邪魔されずに集中できるリアルな場でのコミュニケーションは、心を打ち明けるような深い対話に向いているのではないでしょうか。
「どんどん新しいサービスを」fibonaだからこそ挑戦したいこと
──最後に、fibonaの活動を通して成し遂げたいこと、野望を教えてください。
岩永:
社内外を交えたイベントを企画、運営する立場として、参加者一人ひとりの「何かが好きだ」「何かをやりたい」という自発的な熱量を無理なくつなげるような機会の提供をしていきたいです。
自分の見た目や属性から離れることのできるオンラインでのコミュニケーションは、偏見のない、誰も除外することがないコミュニティ作りに役立つと信じています。個々がやりたいことをお互いに応援しあい、それぞれの幸せを強く感じられるようなコミュニティ作りに貢献できたら理想的ですね。
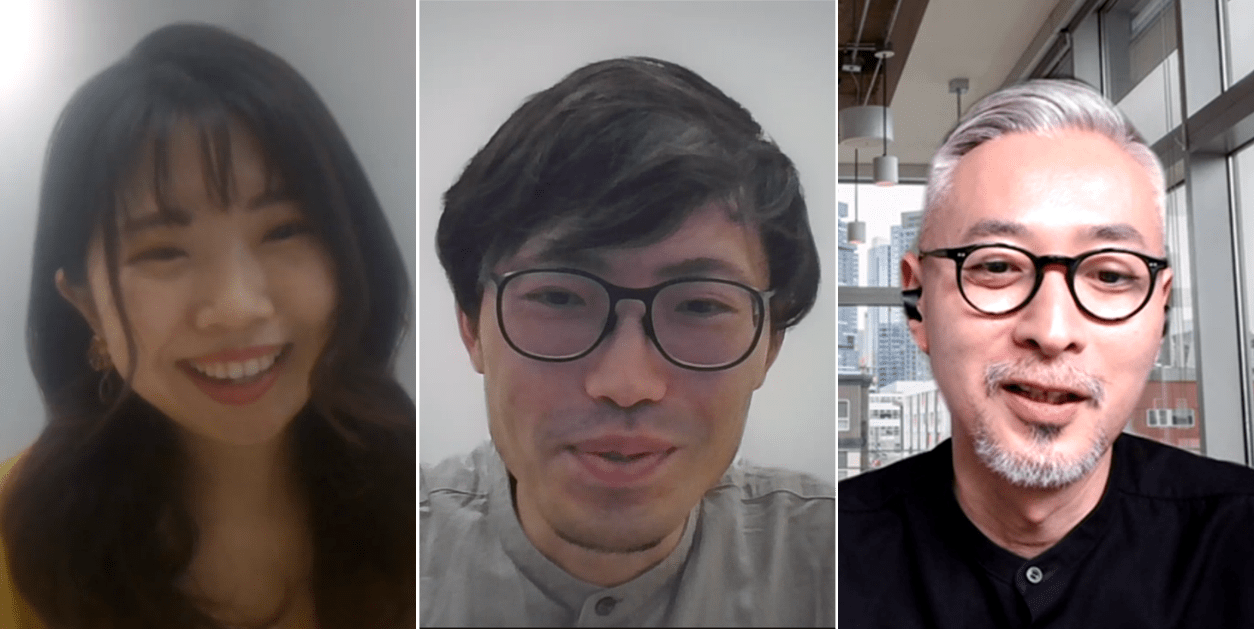
岩下:
fibonaでは、研究員の持っている知識やアイデア、開発の背景などを、お客さまや他の企業に対して発信するだけでなく、それに対するリアクションも拾いながら双方向でコミュニケーションしていくようなプロモーションができたらと考えています。
私がPCや携帯電話を持つ年齢のときには、すでにSNSが普及していました。一ユーザーとして、情報をきちんと取捨選択したり、根拠をもって情報発信をしたりしなければならないという意識をずっと持ってきた世代です。情報が溢れている時代だからこそ、研究員が発信する根拠がある情報は、お客さまからの信頼につながるはず。私たちの発信は、お客さまが製品やサービスをもっと愛してくれるようになるきっかけになると考えています。社内に対しても、fibonaの取り組みの面白さやユニークネスを伝え、参加してみたいと思える人を増やしていきたいですね。
新井:
研究員の方たちの積み重ねてきた研究や技術を可視化したり、外部の企業の人と手を組んだりすることで、新しいサービスをどんどん生み出して行きたいです。
たくさんサービス化をすれば当然、失敗もするでしょう。むしろそこからトライ・アンド・エラーを繰り返してもよいという「失敗する文化」が根付くといいなと思います。たくさんの失敗を経て、質の高いサービスが生まれ、ゆくゆくは日本発のグローバルサービスを作ることができたらいいなと考えています。
(text: Yue Arima edit: Kaori Sasagawa)
Other Activity
4年間の“共創”が集結。ユーザーの未来を拓くプロトタイプと多様なビューティー体験:fibona Open Lab 2023【15のエキシビション】
2024.03.282019年7月より始まった“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボ...
サウナ・温泉愛好家が集合、「蘇湯」が導くこれからのウェルネス: fibona Open Lab 2023【Day2トークセッション&薬草湯WS】
2024.03.21“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。 fibonaでは...
トップクリエイターと研究員が探求、「セカンドスキンメイク™」が拡張する未来のビューティー:fibona Open Lab 2023【Day2トークセッション&WS】
2024.03.13“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。 2023年12月...
行政、ファッション業界、美容業界――垣根を超えて共創し、未来をつくる:fibona Open Lab 2023【Day1トークセッション】
2024.02.15“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。 fibonaでは...